 |
|
|
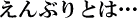 |
【えんぶりって何?】
八戸市及び周辺町村で行われている、一年のはじめに今年の豊作を神様に祈る芸能です。
特徴的な烏帽子(えぼし)をかぶった太夫(たゆう)とよばれる人が、えんぶり唄にあわせて舞います。そして、太夫の舞の間に「松の舞」「えびす舞」「大黒舞」「えんこえんこ」などの祝福芸が舞われます。
もともとは小正月(1月15日)に行われていましたが、現在は2月17日から20日まで行われます。(当えんぶり組は21日まで町内を練り歩きます。)
えんぶり組は、太夫、各芸の舞い手、唄い手、笛・太鼓・手びらがねなど20人ぐらいで、各町内で組織されます。 |
 |
|
 |
【えんぶりの由来】
田をならす道具に、杁(えぶり)というTの字型の道具があります。この道具を持って舞ったことからえんぶりと呼ばれるようになりました。 |
|
【起 源】
日本人は農耕民族であり、特に米作りが重要でしたので、各地に米の豊作を祈る芸能が伝えられています。これを「田楽」といいます。田楽は奈良時代の『日本書紀』にすでにみることができます。
これをもとに、鎌倉時代には農作業を模した舞などをする「田植踊り」という芸能が成立します。
えんぶりは、この「田植踊り」のひとつです。
ですから、えんぶりの起源は、えんぶり唄の歌詞の中に「鎌倉」の言葉がでてくることもあり、鎌倉時代と考えられています。 |
 |
|
 |
【「ながえんぶり」と「どうさいえんぶり」】
えんぶりには、「ながえんぶり」と「どうさいえんぶり」という型があります。
「ながえんぶり」は、藤九郎(とうくろう)とよばれる舞い手のリーダーひとりが、独特な動きで舞います。また、藤九郎の烏帽子に大きなボタンの花がついています。「どうさいえんぶり」は、太夫全員が同じ舞をします。烏帽子にはテープ状の前髪がついています。
「ながえんぶり」が古い型と伝えられていますが、現在ではほとんどが「どうさいえんぶり」になっています。中居林えんぶり組は「ながえんぶり」の型を伝えています。
明治にえんぶりが再興され、えんぶり組同士のもめごとを取り締まるために取締組が置かれました。えんぶりは、もともと神事につながるので礼儀作法を固く守ることを要請されていたのです。
「取締組」には糠塚えんぶり組、内丸えんぶり組、十一日町えんぶり組、横町えんぶり組、売市えんぶり組、中居林えんぶり組の6組が該当します。
年番取締り方法で第一区先取締、第二区中取締、年番御供、第三区取締、第四区取締、第五区取締、この要領で年番組替方法で行事役目が割り当てられます。
【御前えんぶり】
重地えんぶり組、大久保えんぶり組、妙えんぶり組、八太郎えんぶり組、平内えんぶり組、妻ノ神えんぶり組、仲町えんぶり組が御前えんぶりとしされています。
この7組は、年番制で、毎年長者山新羅神社神殿前で奉納摺りを納めた後に三日町、六日町において一斉摺りに参加した後、三八城神社神殿前で奉納摺りをした後と八戸市庁玄関前で、南部家臣、八戸市長、観光協会長等関係各位の臨席の前において奉納摺りを行います。
|
 |
 |
|
|
【一斉摺り】
2月17日には、八戸市他周辺町村からも30組あまりのえんぶり組が長者山に集まり、行列し、全部の組が一斉に摺る「一斉摺り」が八戸市街で行われます。
長者山を出発した行列は神明宮前を通り、ノロシを合図に、十三日町・三日町・六日町・ヤグラ横町で一斉摺りを行います。
この行列の順番ですが、取締組を除いては受付順で決まるので、前日(前々日?)から長者山に行き早い順番を取る組もあるようです。
※中居林組は取締組なので、予め順番が決まっています。
【そのほかの行事】
えんぶり期間中、以下の行事が行われます。
■えんぶり撮影会(17日 無料・長者山新羅神社)
■御前えんぶり(17日 無料・市庁前広場)
■お庭えんぶり(有料・更上閣)
■かがり火えんぶり」(無料・市庁前広場)
■えんぶり公演(有料・公会堂)
各行事の時間、出演組は、(社)八戸観光協会(0178-23-4711)にお問い合わせください。
また、当組の出演予定等についてはFacebookに記載します。
|
 |
 |
|
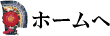 |

